幼少のころ、私は日舞を習っていました。
その記憶はおぼろげながらも、先日見つけた一枚の古い写真によって、当時の情景が鮮やかによみがえってきました。
3~4歳の頃なので、57年ほど前のものだろうか…。
写真の中の私は小さな傘を持っていので、おそらく、初めての舞台で「雨降りお月さん」を踊ったのだろうと思います。
年老いた母が懐かしそうに話してくれたのは、「お化粧して、簪をつけないと踊らないって、駄々をこねたのよ」と。
小さな自分は、舞台で踊る人たちの、艶やかな衣装の美しさに憧れを抱いていたのでしょう。
当時は、まだ芸者さんが多く、私は彼女たちと一緒にお稽古をしていました。
彼女たちの凛とした立ち居振る舞いや、美しく結い上げられた日本髪に、幼いながらも心惹かれていたのかもしれません。
私たちにお稽古をつけてくださったのは藤間勘慶朗先生。
清元 志佐雄太夫の名の方が、より知られているでしょうか。
歌舞伎座の舞台で浄瑠璃方を務められた名匠であり、その指導の場に私も混ぜてもらっていたのです。
しかし、その頃の綺麗な芸者さんたちも、藤間勘慶朗先生も、すでに泉下の人となってしまいました。
時の流れは早いものです。、
芸事というのは、ゆとりのある時代に発展するものなので、もはや衰退は避けられないのかもしれません。
それでも、せめて歌舞伎だけは残ってほしいと願っています。
私には、日本髪や、着物や帯の多様な技法は、もはや歌舞伎の世界でしか守ることができないのではないかという持論があります。
三味線や唄も同じ。
芸者文化の衰退も、時代の流れの中では当然のことなのでしょう。
お座敷で日舞を舞ったとしても、その美しさや意味を理解するお客は、もはや希少だからです。
明治維新の際、日本人は文明開化と称し、和服と日本髪を手放しました。
それでも今日まで、かろうじて残ってきたことは奇跡に近いのかもしれません。
たとえわずかでも、日本の伝統が受け継がれていくことを願わずにはいられない、そんなことを思わせた古い一枚の写真でした。

ランキングのポチ押応援して頂けると嬉しいです。

宜しかったら、こちらの記事もお読みいただければと思います。
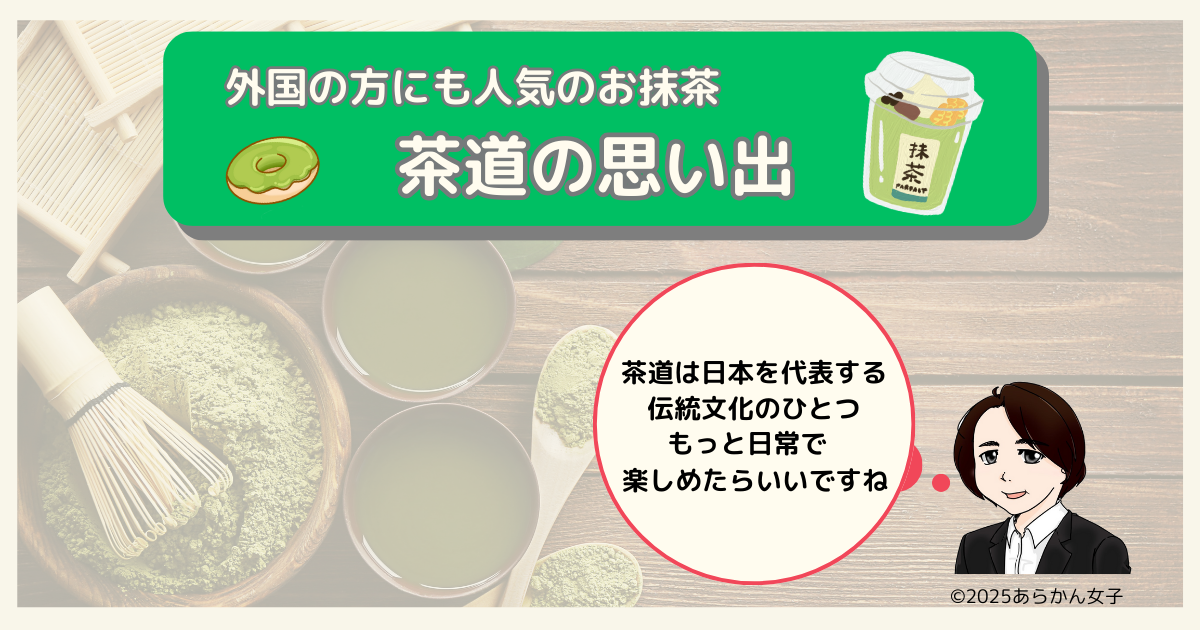
野点セットですが、お家で気軽に楽しむのにも良いですよ。
 | 【茶器/茶道具 野立籠(野点籠)/野点セット(野立セット)】 竹籠バッグ巾着6点セット 当店オリジナル 価格:9988円 |
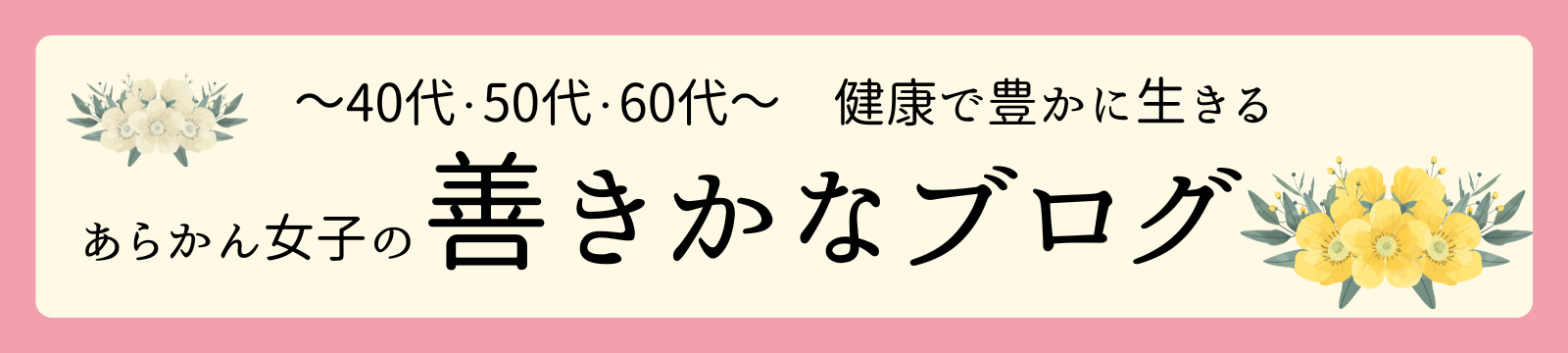


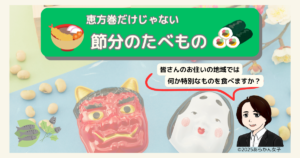
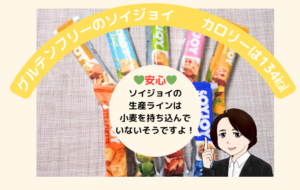

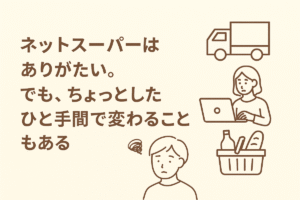

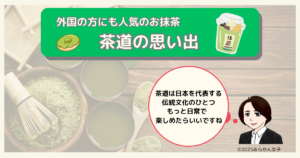
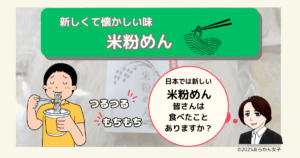
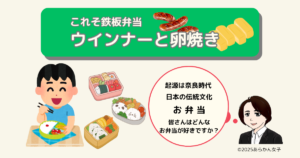
コメント