新しい歳神様を迎えて、その年の無事を願うお正月。日本の年中行事の中では最も古い歴史があると言われています。
農耕が発達したことに伴い、年の始めに豊作を祈念するようになり、歳神様を祀る行事となったそうです。
参考:北海道神社庁
お正月といえば、お節料理が頭に浮かびますよね。
一年に一度、お正月にしか食べられない「ハレの日」のご馳走です。
現実的には、年末年始の物入りで頭を抱えるわけですが。
このお節料理、元々は節日(節句)に神様をお祀りする宮中行事で作られる料理のことで、節日のうち最も重要なのが正月であることから、正月料理を指すようになったのだとか。
私たち庶民がお節料理を口にできるようになったのは江戸時代になってからだそうです。
お節料理は歳神様と食事をともにすることで福を招き災いを打ち祓うされています。
また、歳神様を迎えるときは煮炊きなどを慎むとともに、料理を作る人が骨休めできるようにという意味もあり、冷めてもおいしくいただける工夫=保存が利く工夫がなされています。
現代には好まれない味付けや作る手間もかかることから、お店で購入する方がほとんどだと思います。
わが家ではそれさえもしなくなり、伊達巻、かまぼこ、数の子を買い、あとは筑前煮をつくるだけになりました。食べる物しか作りません。
食文化の継承はなかなか難しいものですが、お節料理の本質は歳神様をお迎えしともに祝うことですから、その気持ちは大切に繋いでいきたいですね。
宜しければクリックお願い致します↓

 | 米粉パン 食パン(1.5斤)4本&コッペパン6本セット ノングルテン米粉100%使用【冷凍でお届け】 ゴルマール 価格:7080円 |
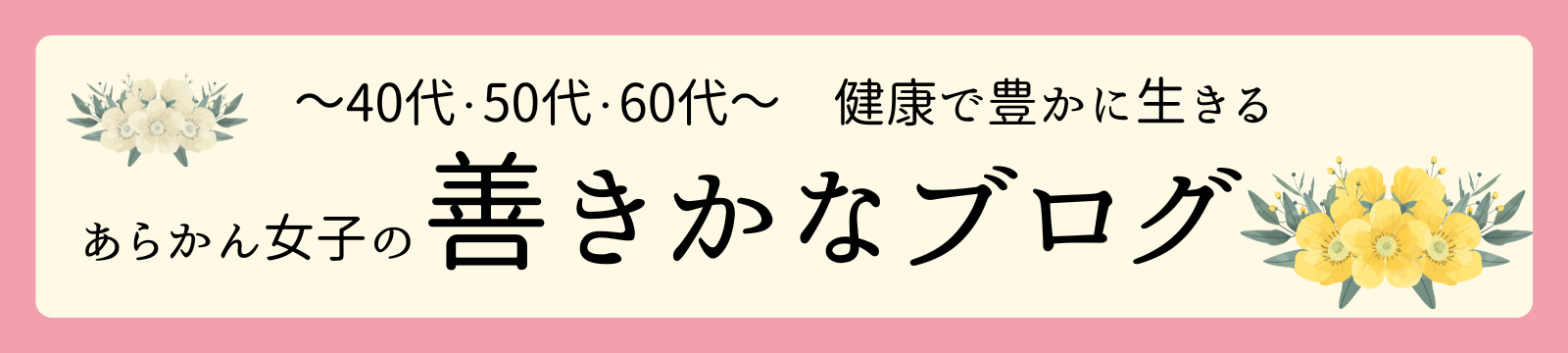

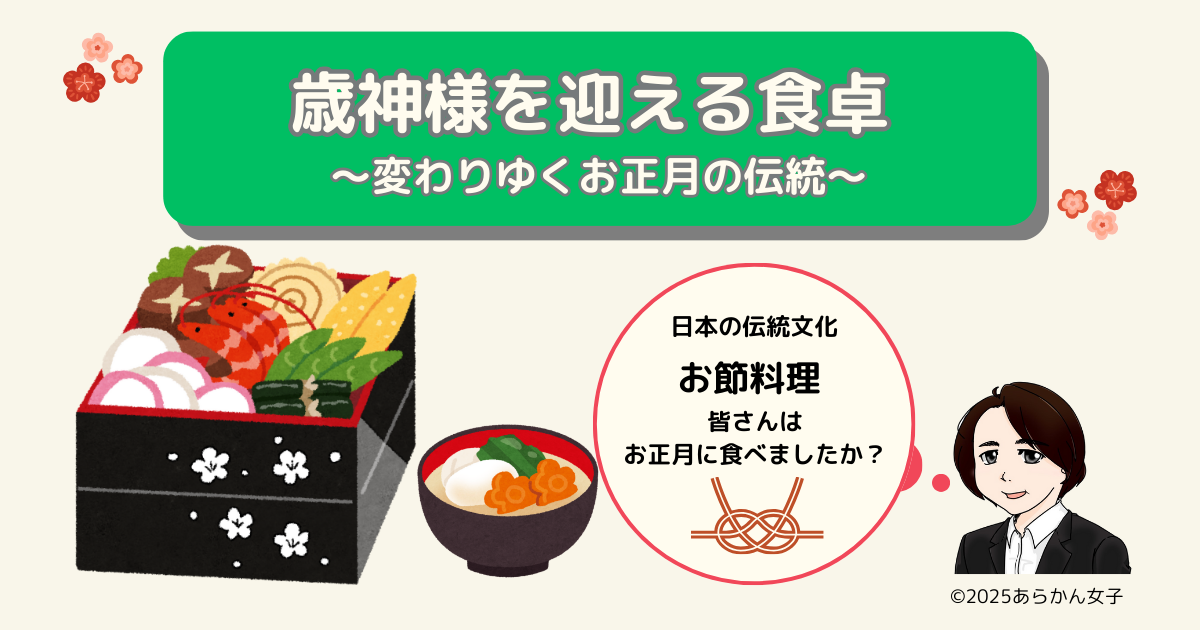

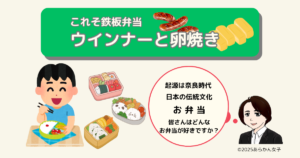

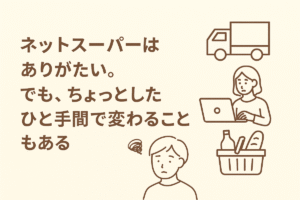

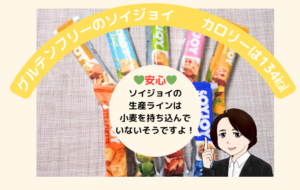

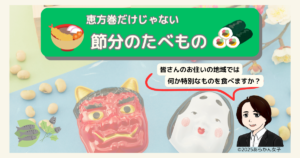
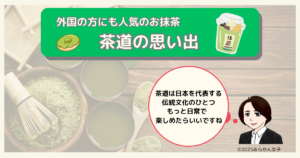
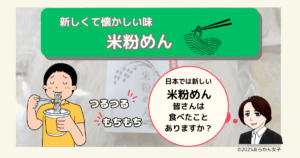
コメント